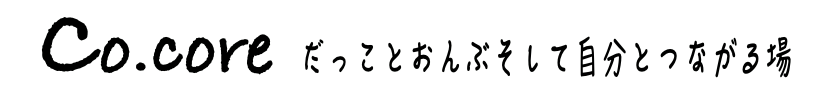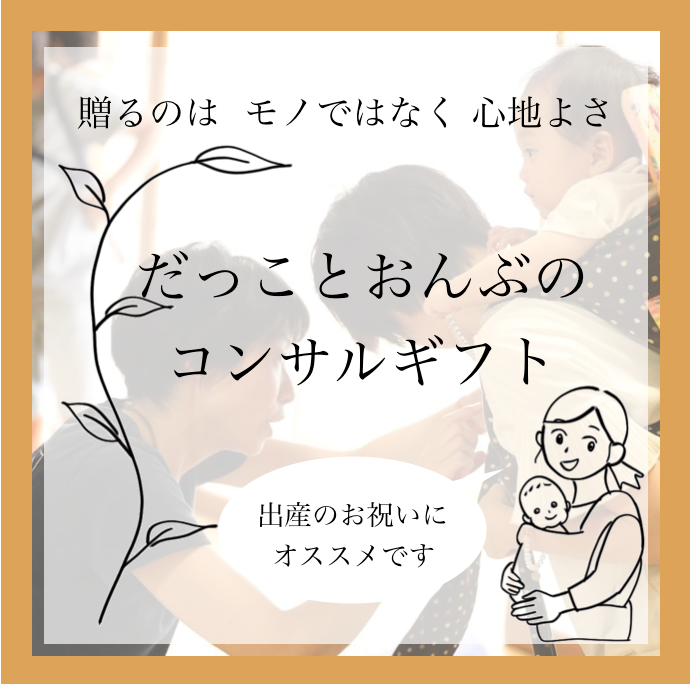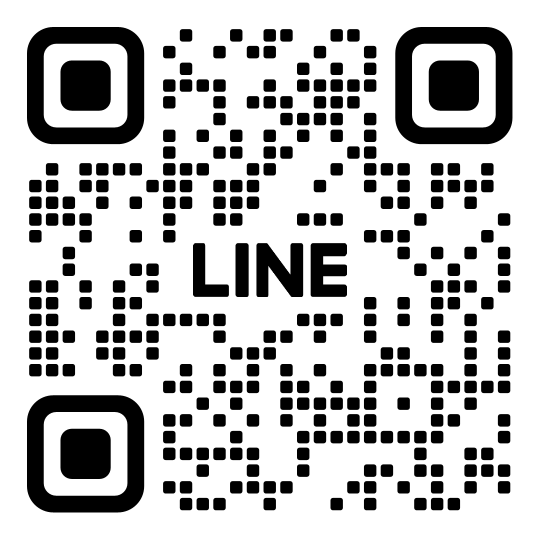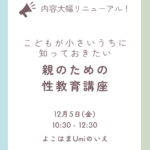よこはま文化活動おすすめ(1)_映画『カナルタ 螺旋状の夢』

画像は akimi Otaさんの公式ページよりお借りしました
https://akimiota.net/Kanarta-1
先日はじぶんのための文化活動の日inよこはま
楽しかったので勝手にオススメします
ながいので今回その(1)
この日が、午前は映画を見て、午後は個展へ行きました
映画は『カナルタ 螺旋状の夢』
https://ideasforgood.jp/2021/09/24/kanarta/
あらすじなどはサイトを見れば分かるので、感じたことを残したいと思います
感じたことはたくさんあるのだけど
特に心に残った2つ
アマゾン先住民のセバスティアンが日本人のナンキ(たぶん太田監督のこと)をとても受け入れていて、自分の言っていること、信じていることは
『お前にもわかる』
と信じているところが、とても印象的だった
もちろんそれまでに時間をかけていろんな交渉があったり、信頼を築くまでにいろんなプロセスがあったとは思うのだけど
(実際、太田監督は1年かけてアマゾンに入り暮らしに密着したとのこと)
自分達の自然観
ビジョンを見ること
ビジョンに導かれることも
『ナンキにもわかる』ということが
風が吹けば植物がサワサワいうよね
水は高いところから低いところへと流れるよね
人間は生まれたらいつか必ず死ぬよね
と同じくらい当然起こり得るという、彼らの確固たるスタンスに、ずっと惹きつけられていた
たぶんわたしにとって
『信じる、既に”ある”を信じる』
がいまの自分のテーマなんだなと思う
そして、歌
彼らは歌う
上手くとか、何かに合わせるとかではなくて
自分の中の何かと会話するように歌を歌う
呼吸をするように歌う
こんなふうに歌うことってあったかなぁと
唯一あったのは子守唄くらいだろうか
それでもあの時は自分の意識を保っために歌っていた気がして、彼らの歌との向き合い方とニュアンスが異なる
歌というのは学校で習うもの、カラオケのために覚えるもの、どこかに評価がチラつき、それははずかしさもともなうものだった
本来、歌というのは自分のなかに湧いてきた感情をそのまま表現するものだったとおもうし、まだ文字が出てくる前から、その民族の知恵を伝承するためのものでもあったとおもう(だから、ごろあわせにすると覚えられる)
それがいつしか、歌(音楽)の本来の役目を見失っているのかもしれない、ということを映画を見ながら感じる
11/19(金)までは横浜でみれますよ!
https://cinemarine.co.jp/schedule/